はじめに
業務効率化や多様な働き方の実現を目指し、多くの企業がGoogle Workspaceの導入を進めています。しかし、その一方で「クラウドサービスのセキュリティは本当に万全なのか?」「導入したのは良いが、何から手をつければ安全に運用できるのか分からない」といった、セキュリティに関する不安の声をよく耳にします。特に企業の機密情報や個人情報を取り扱う上で、セキュリティ対策は経営の根幹に関わる最優先事項です。
Google Workspaceは、Googleの堅牢なインフラと高度な技術に支えられた極めて安全なサービスです。しかし、その安全性を最大限に引き出すためには、導入企業側での「適切な設定」が不可欠となります。初期設定のままでは、意図せぬ情報漏洩や不正アクセスといった重大なリスクを抱え込む可能性があるのです。
「Google Workspaceを導入したいが、セキュリティ面に懸念がある」 「管理者として、まず何を設定すれば良いのか具体的に知りたい」
本記事は、このような課題をお持ちの企業の管理者様、情報システム担当者様に向けて、Google Workspace導入時に行うべきセキュリティ設定を「基本」から「応用」まで網羅的に解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、セキュアな利用環境の構築に向けた、確かな第一歩を踏み出すことができます。
関連記事:改めて知りたい「Google Workspace とは」- 機能・メリット・活用法をDX視点で解説
なぜ導入時のセキュリティ設定が最重要なのか?
クラウドサービスのセキュリティは、サービス提供事業者(Google)と利用者(導入企業)の双方が責任を分担する「責任共有モデル」に基づいています。Googleはインフラやサービスの基盤部分のセキュリティを担保しますが、アカウント管理、アクセス制御、データ共有のルール設定といった運用面のセキュリティは、すべて利用企業側の責任範囲です。
情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ10大脅威 2024」においても、「内部不正による情報漏えい」や「不注意による情報漏えい(誤操作)」が常に上位に挙げられています。これは、強固なシステムだけでなく、それを利用する人間の運用体制がいかに重要かを示唆しています。
Google Workspace導入直後のデフォルト設定は、利便性を考慮して比較的緩やかに設定されている項目もあり、必ずしも全ての企業のセキュリティポリシーに合致するとは限りません。これを放置すれば、不正アクセスや情報漏洩のリスクを著しく高めてしまいます。だからこそ、導入初期の段階で自社のポリシーに合わせて設定を最適化することが、企業の情報を守る上で極めて重要なのです。
関連記事:改めて、クラウドセキュリティの「責任共有モデル」とは?自社の責任範囲と対策をわかりやすく解説
設定の要「Google Workspace 管理コンソール」とは?
Google Workspaceの各種設定は、管理者権限を持つユーザーが「管理コンソール」で行います。これは、組織全体のGoogle Workspace環境を統制するための中枢機能です。ユーザー管理からサービスの有効化、そして本記事で解説するセキュリティ設定まで、あらゆる管理操作をこのWeb画面から行います。
セキュリティ設定を始めるには、まず管理コンソール (https://admin.google.com/) に管理者アカウントでログインしてください。本記事でご紹介する設定は、すべてこの管理コンソール内で行います。
関連記事:
【初心者向け】Google Workspace管理コンソールとは?主要機能と導入時の初期設定ガイド
【フェーズ1】最低限行うべき基本のセキュリティ設定
まずは、組織のセキュリティレベルを底上げするために、すべての管理者が最初に着手すべき必須の基本設定を4つご紹介します。
①アカウント保護の原点:2段階認証プロセスの強制
なぜ必要か? IDとパスワードによる認証は、万が一漏洩した場合、第三者による「なりすまし」を容易に許してしまいます。2段階認証は、パスワードに加えてスマートフォンへの確認コードやセキュリティキーといった本人しか持ち得ない要素を追加で要求することで、不正ログインのリスクを劇的に低減させます。これは、Google Workspaceのセキュリティにおける最も基本的かつ効果的な対策です。
設定のポイント
-
全ユーザーへの強制適用: 管理コンソールで、組織内の全ユーザーに対して2段階認証を強制する設定を有効化します。猶予期間も設定できますが、セキュリティの観点から可能な限り早期の適用を強く推奨します。
-
認証方法の管理: 確認コード、Google認証システムアプリ、セキュリティキーなど、利用を許可する2段階認証の方法を選択します。物理的なセキュリティキーはフィッシング対策として非常に有効であり、弊社のお客様でも管理者や役員層から導入を進めるケースが増えています。
関連記事:
不正ログインを防ぐ!Google Workspace 二段階認証プロセスの基本と設定方法【入門編】
Google Workspace アカウント乗っ取りを防ぐための管理者と従業員のためのセキュリティ対策【入門編】
②不正アクセス対策の基礎:パスワードポリシーの強化
なぜ必要か? 「password123」のような単純なパスワードや、長期間変更されていないパスワードは、攻撃者にとって格好の標的です。強固なパスワードポリシーを強制し、ユーザーに遵守させることで、アカウント侵害のリスクを大幅に軽減します。
設定のポイント
-
文字数と複雑さ: パスワードの最低文字数を12文字以上に設定し、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる要件を強制します。
-
パスワードの再利用禁止: 過去に使用したパスワードの再利用を禁止し、使い回しによるリスクを防ぎます。
-
有効期限の設定: 定期的なパスワード変更を促すため、有効期限(例: 1年)を設定することも有効な手段です。
③情報漏洩リスクの低減:Googleドライブの共有設定
なぜ必要か? Googleドライブのファイル共有は非常に便利ですが、設定ミスは深刻な情報漏洩に直結します。特に「リンクを知っている全員」への共有設定や、組織外への共有は、意図せず機密情報をインターネット上に公開してしまうリスクをはらんでいます。
設定のポイント
-
組織外共有の制限: デフォルトで組織外ユーザーとの共有を許可するかどうかを厳格に設定します。まずは「オフ」から始め、必要に応じて特定の信頼できるドメイン(取引先など)のみを許可するホワイトリスト方式を検討するのが安全です。
-
リンク共有のデフォルト設定の変更: 新規ファイルのデフォルトのリンク共有設定を、最も安全な「制限付き」(追加されたユーザーのみがアクセス可能)に変更します。
関連記事:
Googleドライブで安全にファイルを共有するには?基本設定と重要ポイントを解説
④シャドーIT対策:サードパーティ製アプリ連携の管理
なぜ必要か? Google Workspaceは多くのサードパーティ製アプリと連携できますが、その中には悪意のあるアプリや、必要以上のデータアクセス権限を要求するアプリも存在します。管理者が把握していないアプリ利用(シャドーIT)は、重大なセキュリティインシデントの温床となり得ます。
設定のポイント
-
APIアクセスの制御: 信頼できるアプリのみを許可リストに追加し、それ以外のアプリ連携をブロックする設定を検討します。
-
アクセス権限の監査: 定期的に、各アプリが要求しているアクセス権限(スコープ)を確認し、過剰な権限を持つアプリや不要になったアプリのアクセスを取り消す運用が重要です。
関連記事:
【入門編】シャドーIT・野良アプリとは?DX推進を阻むリスクと対策を徹底解説【+ Google Workspaceの導入価値も探る】
【フェーズ2】セキュリティをさらに強化する応用設定
基本設定を終えたら、次はより能動的に脅威を検知し、防御するための応用設定に進みます。
①脅威の早期発見:アラートセンターの活用
なぜ必要か? アラートセンターは、不審なログイン試行、管理者権限の変更、フィッシングの疑いがあるメールなど、潜在的なセキュリティリスクを検知し管理者に通知する機能です。これを定期的に確認する体制を築くことで、インシデントの早期発見と迅速な対応が可能になります。
設定のポイント
-
通知ルールの設定: 特に注意すべき重要なアラート(例: 「海外からの不審なログイン」)が発生した際に、管理者にメールで通知が届くように設定します。
-
定期的な確認の習慣化: 通知任せにせず、週に一度はアラートセンターのダッシュボードを確認し、異常がないかをチェックする運用を強く推奨します。
②標的型攻撃への対策:Gmailの高度な保護設定
なぜ必要か? ビジネスメールを狙ったフィッシング詐欺やなりすましメールは、依然として企業にとって大きな脅威です。Gmailのセキュリティ設定を強化することで、これらの脅威が従業員に届く前段階でブロックできる可能性が高まります。
設定のポイント
-
添付ファイルの保護: 添付ファイル内のマルウェアや不正なスクリプトをスキャンする設定を有効にします。
-
なりすまし対策: 送信ドメイン認証技術(SPF, DKIM, DMARC)の設定を正しく行い、自社ドメインをかたった「なりすましメール」を防止・検知します。これは技術的な設定を要するため、専門家の支援を仰ぐことをお勧めします。
関連記事:【入門編】Gmailの迷惑メール・フィッシング詐欺対策を解説 ビジネスを守る基本設定
③インシデント調査の準備:監査ログの確認
なぜ必要か? 万が一セキュリティインシデントが発生した際、「いつ、誰が、何をしたか」を追跡するために監査ログは不可欠です。どのようなログが取得できるのかを事前に把握し、定期的に確認しておくことが、有事の際の迅速な調査に繋がります。
設定のポイント
-
ログイン監査: ユーザーのログイン履歴、特に失敗した試行や通常と異なる場所からのアクセスがないかを確認します。
-
管理者アクティビティ監査: 管理コンソール内での操作履歴はすべて記録されます。意図しない設定変更が行われていないかを定期的にチェックします。
関連記事:【入門】Google Workspace 監査ログとは?基本的な確認方法とセキュリティ活用の考え方
④高度なセキュリティ対策
企業のコンプライアンス要件や、より高度なセキュリティ統制が求められる場合、Google WorkspaceのEnterpriseエディションなどで提供される以下の機能が有効です。
-
データ損失防止(DLP): マイナンバーやクレジットカード番号などの機密情報を含むファイルが、社外へ送信・共有されるのを自動的に検知し、ブロックします。
-
コンテキストアウェアアクセス: ユーザーの場所、デバイスのセキュリティ状態、IPアドレスなどに基づき、Google Workspaceへのアクセスを動的に制御する「ゼロトラスト」モデルを実現します。
-
セキュリティセンター: 脅威の分析、インシデント調査、推奨される対策の提示などを一元的に行う、高度なセキュリティ管理ダッシュボードです。
これらの機能を活用することで、さらにセキュリティレベルを飛躍的に高めることが可能です。
関連記事:
【入門編】DLPとは?データ損失防止(情報漏洩対策)の基本をわかりやすく解説
Google Workspaceのコンテキストアウェアアクセスとは?セキュリティ強化の第一歩をわかりやすく解説
今さら聞けない「ゼロトラスト」とは?基本概念からメリットまで徹底解説
設定に不安を感じたら?XIMIXによるセキュリティ強化支援
「自社だけで設定するのは不安」「我々の業界で求められるセキュリティレベルが分からない」 「高度な機能を導入したいが、設定や運用が難しそうだ」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちXIMIXにご相談ください。 XIMIXは、数多くの中堅・大企業様の導入をご支援してきた実績に基づき、お客様のビジネスとセキュリティ要件に最適なご提案を行います。
-
現状分析と最適な設定のご提案: お客様の現在の設定状況を診断し、企業ポリシーに合わせた最適なセキュリティ設定を具体的にご提案します。
-
高度なセキュリティ機能の導入支援: DLPやコンテキストアウェアアクセスといった高度な機能の導入・設定から、従業員へのトレーニングまでを一貫してサポートします。
-
継続的な運用アドバイス: セキュリティは一度設定すれば終わりではありません。継続的なモニタリングと改善について、専門家の立場からアドバイスを提供します。
XIMIXのGoogle Workspace 導入支援についてはこちらをご覧ください。
XIMIXのGoogle Cloud 導入支援についてはこちらをご覧ください。
まとめ:セキュリティ設定は継続的な取り組み
Google Workspaceは、正しく設定・運用すれば、企業のDXを加速させる非常に安全で強力なツールです。その安全性を確固たるものにするためには、導入企業側の主体的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
最後に、本記事で解説したセキュリティ設定のチェックリストをまとめます。
【セキュリティ設定チェックリスト】
-
[ ] フェーズ1:基本設定
-
[ ] 全ユーザーへの2段階認証プロセスの強制
-
[ ] 強力なパスワードポリシー(文字数、複雑さ、再利用禁止)の設定
-
[ ] Googleドライブの共有設定の見直し(組織外共有・リンク共有の制限)
-
[ ] サードパーティ製アプリ連携の管理と監査
-
-
[ ] フェーズ2:応用・強化設定
-
[ ] アラートセンターの通知設定と定期的確認
-
[ ] Gmailの高度な保護設定(フィッシング・なりすまし対策)
-
[ ] 監査ログの定期的な確認体制の構築
-
[ ] (必要に応じて)DLPなど高度なセキュリティ機能の導入検討
-
まずはこれらの設定を確実に実施し、セキュアな利用環境の土台を築きましょう。そして、企業の成長や外部環境の変化に合わせて設定を常に見直し、強化していくことが、安全なDX推進の鍵となります。
- カテゴリ:
- Google Workspace


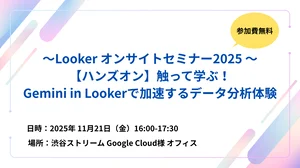

/Google%20Cloud/cloud-modern-interior.png?width=84&name=cloud-modern-interior.png)
/business-collaboration-teamwork.png?width=84&name=business-collaboration-teamwork.png)
/business-process-visualization.png?width=84&name=business-process-visualization.png)
/task-sequence-diagram.png?width=84&name=task-sequence-diagram.png)
/collaborative-problem-solving.png?width=84&name=collaborative-problem-solving.png)
